1. はじめに(富岳NEXTの位置づけ)
スーパーコンピュータ「富岳」の後継となる次世代フラッグシップシステム「富岳NEXT」の開発が、理化学研究所(理研)を主体として2025年より本格的に開始されましたriken.jp。本計画は、日本のHPC(高性能計算)インフラを2030年頃までに刷新し、シミュレーションとAIを高度に融合した世界初のゼタスケール級スーパーコンピュータを実現することを目指す野心的プロジェクトですblogs.nvidia.comxenospectrum.com。富岳NEXTは従来の単なる性能追求に留まらず、「AI for Science」と称される新たな研究パラダイムを支えるAI-HPC統合プラットフォームとして位置づけられていますriken.jpxenospectrum.com。これは、地球環境問題や防災、創薬、先端ものづくり等、日本と世界が直面する喫緊の科学技術課題の解決に資する計算基盤となることが期待されておりblogs.nvidia.com、日本の科学技術力・産業競争力を将来にわたり支える「戦略的投資」として政府も位置づけていますtomshardware.com。
現行の富岳(2020年共用開始)は2021年まで世界1位の性能を記録し、その後も新型コロナ対策のシミュレーションなどで活躍しましたがtomshardware.com、2025年時点では米国や中国のエクサスケール機に後塵を拝し、最新TOP500では7位に後退していますdatacenterdynamics.com。こうした中、富岳NEXTは「ポスト富岳」として日本が再び世界最高水準を狙う計画であり、初めてGPUによるアクセラレーションを日本のフラッグシップ機に導入するなど、従来路線に大きな変革をもたらす点でも注目されていますriken.jpdatacenterdynamics.com。理研・富士通・NVIDIAの三者協力による国際連携体制の下、富岳NEXTは単なる富岳のアップグレードではなく日本の「Made with Japan」戦略を象徴する計算基盤となり、国内の独自技術とグローバルな最先端技術を組み合わせることで次世代の科学的ニーズに応えることが期待されていますblogs.nvidia.comblogs.nvidia.com。
2. 技術的仕様(CPU/GPU構成、性能目標、冷却、ストレージ・ネットワーク、消費電力など)
富岳NEXTのハードウェアは、理研と富士通が開発中の次世代CPU「FUJITSU-MONAKA」の後継チップである**「FUJITSU-MONAKA-X」(開発コードネーム)と、NVIDIAが設計を主導する最新世代のGPUアクセラレータによって構成されるヘテロ性能システムとなりますriken.jp。CPUのMONAKA-Xは、富岳で実績を残したArmベースの「A64FX」の技術を発展させた超多コアアーキテクチャで、2nm世代の最先端プロセス技術を採用しつつ、高度な3Dパッケージングや超低電圧動作回路など富士通独自技術で高性能・省電力・高セキュリティを両立する設計ですdatacenterdynamics.comriken.jp。また世界で初めてArmの行列演算エンジン(SME)をサーバーCPUに内蔵し、CPUだけでもAI推論を低レイテンシで処理可能にするなど、HPCとAIの双方に効く機能強化が図られていますriken.jp。一方のGPUは、NVIDIAが今後投入する大規模並列演算向けの次世代アーキテクチャを採用する見通しであり、現時点で正式な型番は未定ながら「Rubin(ルービン)」世代もしくはそれ以降のアーキテクチャになると推測されていますnextplatform.comnextplatform.com。実際、NVIDIA社のロードマップによれば2025–26年頃に登場予定の“Rubin”アーキテクチャGPU(開発コード名)の次に、2029年頃にはその後継となる“Feynman”世代のGPUが控えるとされておりnextplatform.com、富岳NEXT稼働時期に合わせ最先端のGPU技術が投入されることになるでしょう。これらCPUとGPUを密接に結合するため、富岳NEXTでは「NVLink Fusion」**と呼ばれる新技術が採用されます。NVLink FusionはCPUとGPUをつなぐシリコンブリッジ(チップレット)であり、富士通製CPUとNVIDIAアーキテクチャ間に極めて高速・広帯域のデータ接続を実現するものですdatacenterdynamics.com。これによりCPUとGPUのメモリ空間を効率的に共有し、大量データを扱うAI学習やGPU計算で発生するボトルネックを低減しますnextplatform.com。加えて、ノード内では次世代のNVSwitchによる多数GPU相互接続が図られるほかnextplatform.com、ノード間も新規開発の広帯域・低レイテンシネットワークが導入される予定で、システム全体で大規模計算に耐える通信インフラが構築されますhpcwire.jp。ストレージについてもAI時代のI/O要件に応える高速ストレージが求められておりhpcwire.jp、大容量のフラッシュストレージや分散ファイルシステムなど先進的な手法の採用が検討されていますxenospectrum.com。
性能目標の面では、富岳NEXTは現行の富岳と比較してハードウェア性能で5倍以上、ソフト・アルゴリズム最適化による効果も含め実アプリケーションで最大100倍もの性能向上を狙っていますriken.jpriken.jp。富岳が「京」から40倍のハード性能向上(100倍の一部アプリ性能向上)を達成した実績になぞらえ、今回も10~20倍のアルゴリズム革新(AIによる計算代替や効率化など)と組み合わせることで桁違いの飛躍を目指すというロードマップですriken.jp。具体的な数値として、HPC分野で重視される倍精度(FP64)性能は総計で2~3エクサフロップス級(富岳の約0.5EFLOPSの5~6倍)を視野に入れ、AI分野で用いられる低精度(FP8)ではスパース演算込みで600エクサフロップス(EFLOPS)超という驚異的な目標値が掲げられていますdatacenterdynamics.comriken.jp。後者は1ゼタフロップス(=1000エクサ)に迫る規模であり、計算方式の違いはあるものの「世界初のゼタスケール・スーパーコンピュータ」として位置づけられていますdatacenterdynamics.com。この飛躍的性能はあくまで実効性能の向上に主眼が置かれており、AIと従来型シミュレーションを組み合わせた**「AI融合HPC」で50エクサフロップス以上の実効性能を上げることが目標とされていますxenospectrum.comxenospectrum.com。電力消費に関して特筆すべきは、こうした大幅な性能強化を現在の富岳とほぼ同じ消費電力枠(約40MW)以内で実現しようとしている点ですriken.jptomshardware.com。富岳NEXTではCPU・GPUの省エネ設計や高速冷却技術の導入、そしてソフト面での効率化によって電力あたり性能を劇的に向上させ、限られた電力で最大の成果を引き出すことが追求されています。特に冷却面では温水冷却(Warm Water Cooling)**方式への対応が求められており、チラー(冷却機)を使わず比較的高い水温で機器を直接冷却することで冷却エネルギーを削減する設計になっていますhpcwire.jp。この温水液冷の採用や高密度実装技術により、データセンター全体としてカーボンニュートラルに近づける工夫も盛り込まれる予定ですmext.go.jppccluster.org。
3. 開発スケジュール(2025年時点の最新ロードマップ)
富岳NEXT開発のロードマップは2024年度から始動し、2030年頃の本格稼働をゴールに設定されていますriken.jp。2024年には文部科学省(MEXT)のHPCI計画推進委員会による報告書がまとめられ、富岳の後継機開発方針(世界初のゼタ級を目指すこと等)が提言されましたdatacenterdynamics.comxenospectrum.com。これを受けて2025年1月に理研が開発開始を正式に表明しriken.jp、同年3月には現在の富岳が設置されている神戸市ポートアイランド地区(理研計算科学研究センター敷地)に隣接する用地に富岳NEXTの新施設を建設する計画が発表されましたriken.jp。富岳NEXTは現行富岳の隣に新設され、システム入替に伴う計算資源の「空白期間」が極力生じないよう配慮されていますriken.jpriken.jp。2025年6月には富士通が富岳NEXTの基本設計業務を受注し、翌2026年2月末まで基本設計フェーズを担当する契約が締結されましたfujitsu.comfujitsu.com。この基本設計段階ではシステム全体構成やノード設計、CPUアーキテクチャの仕様策定が行われ、並行してNVIDIAとも協働しGPUとインターコネクトの検討が進められますriken.jpblogs.nvidia.com。2025年夏にはNVIDIAを正式に開発パートナーに加えた国際連携体制が発足し、東京でローンチセレモニーが開催されましたblogs.nvidia.comblogs.nvidia.com。これによりハード・ソフトのコデザインが本格化し、以降2026年からは詳細設計・試作段階に移行する計画ですmonoist.itmedia.co.jp。富岳NEXT用CPUの開発ロードマップ上、2027年頃までにMonaka-X試作チップが完成し、その後GPU最適化や周辺技術を統合した最終設計が固まる見通しですnextplatform.com。システムの据え付け・組み立ては2028年~29年頃に実施され、テスト運用を経て2029年度末から2030年初頭に本格稼働開始というタイムラインが目標となっていますnextplatform.comriken.jp。現時点では約3,400ノード規模のシステムを想定しておりnextplatform.com、富岳(約432筐体・159,000ノード)と比べノード数自体は絞り込んだ構成になる可能性がありますが、その1ノード当たりの性能は飛躍的に向上する計画です。また理研R-CCS内では、富岳NEXTの本稼働に先立ち、開発段階から**「バーチャル富岳」**と称するテストベッド環境をクラウド等で提供し、ソフトウェアの事前開発やユーザコミュニティ育成を進めていますriken.jpriken.jp。2026年には大阪で国際会議「SCA/HPC Asia 2026」が開催予定であるなどriken.jp、富岳NEXTを軸に国内外のHPC研究者コミュニティを巻き込んだ人材育成・技術交流も推進されています。
富岳NEXTの整備予定地(赤枠内)が示された神戸・ポートアイランドの航空写真riken.jp。現行「富岳」は赤枠の北側(写真上方)の理研計算科学研究センター内に設置されており、隣接地に新施設を建設して増設する計画となっている(2025年3月発表)。
4. 利用目的・対象分野(AI、気象、生命科学、基礎科学など)
富岳NEXTは、その名のとおり従来からの数値シミュレーション科学に加えて、AI技術を本格的に取り入れた計算プラットフォームとなることで、学術から産業まで幅広い分野のイノベーションに寄与することが期待されていますblogs.nvidia.comblogs.nvidia.com。利用の大きな柱の一つは気候・災害分野で、例えば地球規模の気候変動予測や災害シミュレーションの高精度化です。富岳NEXTでは、地震・津波発生のマルチスケールシミュレーションをAIと組み合わせて高速に実行し、防災・減災に役立てる研究やxenospectrum.com、従来数日がかりだった高解像度気象予測を飛躍的に高速化することで精度と頻度を高め、気候変動対策の立案支援に活かすといった応用が見込まれますxenospectrum.com。第二の柱はライフサイエンス・医療分野です。富岳NEXTは、原子レベルの巨大な生体シミュレーションや創薬シミュレーションを可能にし、AIによる新薬候補分子の探索や分子動態のデジタルツイン構築を大幅に加速するとされていますxenospectrum.com。実際、富岳を用いて13億パラメータ規模で開発された「Fugaku LLM」と呼ばれる基盤的AIモデルをさらに何桁もスケールアップし、創薬や生命科学研究に特化した高度な大規模言語モデルの学習を短期間(2ヶ月以内)で完了できる可能性も指摘されていますxenospectrum.com。第三に、製造業・材料開発など産業競争力強化の分野があります。富岳NEXTではシミュレーションデータを用いた生成AIにより、自動車など工業製品の最適設計案をAIが自動提案したり、新素材の特性を予測するなど、設計開発プロセスそのものの高度化・効率化が期待されていますblogs.nvidia.comxenospectrum.com。特に自動車では、空力シミュレーションとAIを組み合わせたボディ形状の自動最適化や、自動運転AIモデルの大規模訓練などを通じて、開発期間の短縮と安全性向上を両立させる、といった未来像が描かれていますxenospectrum.com。
さらに富岳NEXTは、学術基盤としての基礎科学全般への貢献も重視されています。その象徴が「AI for Science」という理念であり、これはAIが科学研究プロセスの様々な局面を支援・自動化することで、人間の研究者の発見速度を飛躍的に高めるというビジョンですriken.jpblogs.nvidia.com。具体例として、富岳NEXT上では物理シミュレーションの一部をサロゲートモデル(代理モデル)や物理インフォームド・ニューラルネットワーク(PINN)に置き換え計算を高速化したりriken.jp、AIが自動生成したコードや仮説に基づきシミュレーションを実行するといったことが可能になりますriken.jp。これにより、従来は試行錯誤に時間を要した基礎科学の研究サイクル(仮説→実験/計算→解析→次の仮説)がほぼリアルタイムで回るようになり、新材料の発見や新理論の構築が格段にスピードアップすると期待されますxenospectrum.comxenospectrum.com。AIを「科学の新たな装置」として活用するこの試みは、気候・宇宙・素粒子・材料・生命科学などあらゆる基礎研究分野に影響を与える可能性があり、富岳NEXTはそのための標準プラットフォームを世界に先駆けて提供することになりますriken.jpblogs.nvidia.com。なお、富岳NEXTで培われるソフトウェア資産(CUDA-Xライブラリや最適化コンパイラなど)はクラウド等を通じ広く公開される予定であり、大学・研究機関・企業の枠を超えた幅広いユーザーがこのプラットフォームを活用できるよう計画されていますblogs.nvidia.comblogs.nvidia.com。
5. 予算と政府の関与(最新の予算措置を反映)
富岳NEXTの開発・整備には、日本政府(文部科学省)が主導するHPCI計画のもと巨額の予算が投じられる見込みです。2024年の計画段階で総額約1100億円超という試算が示されておりasahi.comtomshardware.com、これは前身の「富岳」(約1100億円)に匹敵する規模となります。実際の予算措置は年次ごとに段階的に行われ、2025年度当初予算には開発費として約73億円が計上されましたeetimes.itmedia.co.jp。初年度は主に基本設計や試作に充てられ、2026年度以降の詳細設計・製造フェーズでも適宜予算が積み増されていく予定ですmonoist.itmedia.co.jp。最終的な投資額は開発の進捗や技術動向に応じて調整されますが、稼働開始の2030年頃までに総額で1000億円規模の国費投入が行われる見通しと報じられていますxenospectrum.com。この予算にはハードウェア開発だけでなく、アプリケーション開発支援や施設建設費、運用ソフト開発費なども含まれており、政府として「ポスト富岳」計画を国家プロジェクトとして包括的にバックアップする姿勢が明確に示されています。
政府の関与は資金面に留まらず、政策的にも富岳NEXTを重要視しています。文部科学省は2024年に富岳NEXTに関する有識者会議を開催し、「世界初のゼタスケール計算基盤の実現」を第6期科学技術基本計画における国家目標の一つに位置づけましたdatacenterdynamics.com。また経済産業省や内閣府も、ポスト5G・次世代半導体と並ぶ重点分野として次世代スーパーコンピュータ開発を支援しており、2023年には関連する半導体技術開発予算(NEDO事業)を通じ富士通のMONAKAプロジェクトに助成が行われていますfujitsu.com。さらには日米科学技術協力の文脈で、米国エネルギー省(DOE)との間でHPC/AI分野の連携協定が締結され、ソフトウェア面の共同研究や人材交流が図られていますriken.jp。富岳NEXTは文部科学省が所管する国家基盤ですが、その恩恵は国内の大学・研究機関・企業に広く提供される予定であり、産学官オールジャパンの体制で利用・成果創出が推進されますblogs.nvidia.comblogs.nvidia.com。具体的には、大学共同利用機関や防災科学研などへの計算資源提供、産業利用課題の公募といった施策が検討されています。
また、富岳NEXTの開発は日本の半導体戦略とも関連しています。本プロジェクトの鍵となるCPU「MONAKA-X」は2nmプロセスでの製造が予定されていますが、その製造には台湾TSMC社の先端ファウンドリを活用する計画ですtrendforce.com。一方で、政府が推進する国内ファウンドリ企業**Rapidus(ラピダス)**も2027年までに2nm量産技術の確立を目指しており、富士通は将来的にRapidusでの製造も視野に入れてサプライチェーン強化に取り組む姿勢を示していますtrendforce.com。実際、富士通社長の時田氏はRapidusへの出資も表明しており、仮にRapidusが間に合えば国産チップとしてMONAKAを製造する可能性もありますtrendforce.com。政府としてもRapidus支援を通じて得た先端半導体技術を富岳NEXTに波及させ、日本発の計算基盤技術として国際的プレゼンスを高める狙いがあります。このように富岳NEXTは、日本政府の科学技術・産業・安全保障戦略の交差点に位置するプロジェクトであり、その成功に向けた官民挙げての投資と支援が進められています。
6. 関連企業・研究機関(富士通、NVIDIA、理研など)
富岳NEXTの開発体制は、主要なステークホルダーである理化学研究所(理研)、富士通、NVIDIAの三者を中心に据えた国際的な連携で進められていますriken.jp。まず理研は、本プロジェクトの主管研究機関として開発全体を統括します。理研計算科学研究センター(R-CCS、神戸)には富岳に続き富岳NEXTも設置される予定で、R-CCS所長の松岡聡氏(富岳の共同開発者でもある)が開発の指揮を執っていますblogs.nvidia.com。理研はHPCアプリケーション開発やアルゴリズム最適化に強みを持ち、富岳NEXTにおいてもソフトウェアスタックの高度化やAI融合アルゴリズムの研究開発を主導しますriken.jpriken.jp。また理研はHPCI計画の中心機関として、国内大学・研究機関との連絡や計算資源の配分、さらにはDOEなど海外機関との調整役も担い、富岳NEXTの成果が広く波及するためのハブとなりますriken.jp。
富士通は、長年にわたり日本の国産スーパーコンピュータ開発を牽引してきたメーカーであり、富岳NEXTでもハードウェア面の要となるパートナーです。富士通は富岳で世界初の商用ArmベクトルCPU「A64FX」を開発しましたが、その後継として社内プロジェクト「MONAKA」を進めていますdatacenterdynamics.com。MONAKAは当初データセンター向け省電力CPUとして2027年商用化予定ですが、富岳NEXT向けに強化したMONAKA-Xが本計画の中核CPUとなりますdatacenterdynamics.comdatacenterdynamics.com。富士通は2025年6月に富岳NEXTの基本設計契約を獲得し、計算ノード全体の設計やCPU開発、システムインテグレーションを担当していますdatacenterdynamics.comdatacenterdynamics.com。CTOの馬場健氏(2023年就任)は「Made-in-JapanのCPU技術で世界をリードする」と意気込みを述べておりfujitsu.com、富岳NEXTの開発経験を将来の国産AIプロセッサ(ニューロモーフィックなど)開発にも繋げたい考えを示していますfujitsu.com。富士通にとって富岳NEXTは、同社のCPU技術を国際市場に売り込む好機でもあり、開発したMONAKA系CPUを他国のスーパーコンピュータやデータセンターにも提供していく構想を掲げていますriken.jp。
NVIDIAは、AI・GPU計算分野で世界をリードする米国企業であり、日本の国家スパコン計画に初めて深く参画する形となりました。CEOのジェンスン・フアン氏が2024年に来日した際、日本に「自国のAIインフラを自前技術とNVIDIA技術で築く」よう呼びかけた経緯もありblogs.nvidia.com、富岳NEXTでの協業はそのメッセージに応えるものとなっています。NVIDIAは富岳NEXTでGPUアクセラレータの設計を主導し、同社最新のGPUアーキテクチャを富士通CPUと高度に接続するNVLink Fusion技術を提供しますblogs.nvidia.com。さらにNVIDIAのCUDA並びにAIソフトウェアスタック(CUDA-Xライブラリ、TensorRT、NeMo等)を富岳NEXTに統合し、ユーザは世界標準のGPUコンピューティングエコシステムをそのまま活用できる環境が整えられますblogs.nvidia.comtomshardware.com。NVIDIA幹部のIan Buck氏(HPC担当VP)は「富岳NEXTは日本の英知とNVIDIA技術の結晶であり、アプリケーションを100倍高速化しつつエネルギー効率も維持する画期的システムになる」と述べていますdatacenterdynamics.com。今回の協業は単に日本がNVIDIAのGPUを購入するだけでなく、**共同設計(co-design)**の形で深く関与している点が特徴ですblogs.nvidia.comblogs.nvidia.com。NVIDIAにとっても、日本の国策スーパーコンピュータに自社技術を提供し共創することは前例のない取り組みであり、このモデルを通じて日本市場でのプレゼンス拡大や、自社GPUと他国CPUの協調動作ノウハウの蓄積といったメリットがあります。
このほか、富岳NEXTには多様な機関・企業が関与しています。文部科学省は予算・政策面の主導官庁として、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)などを通じて本計画を推進しています。また、理研R-CCSの所在地である兵庫県・神戸市も地元企業との連携支援や人材育成で協力しますriken.jp。半導体製造面ではTSMCやRapidusなど先端ファウンドリ企業、AI応用面では国内外のソフトウェアベンダーやクラウド事業者がパートナーになる可能性があります。さらに米国DOEの国立研究所(オークリッジやローレンス研など)とは、Benchmarkプログラムの共同開発やAI応用の情報交換が始まっていますriken.jp。大学コンソーシアムも富岳NEXT対応の人材育成やアプリケーション開発に参画しており、日本全体のHPCコミュニティが一体となった取り組みとなっています。
7. おわりに(将来的な拡張性・国際競争力など)
富岳NEXTは、「京」→「富岳」→「NEXT」へと続く日本のフラッグシップ計算機開発の系譜において、新たな転換点を示すプロジェクトです。システム設計段階から国際連携を取り入れ、国内技術(国産CPU)と海外技術(GPUエコシステム)のハイブリッド型で競争力を高めるアプローチは、日本のHPC戦略としても大きな挑戦と言えます。将来的な拡張性の観点では、富岳NEXTは単体のスーパーコンピュータに留まらず**「計算プラットフォーム」**として発展することが期待されています。例えば、量子コンピュータやクラウド上の分散コンピューティング資源と連携し、必要に応じて計算リソースを拡張・共有できるようなアーキテクチャが検討されていますriken.jp。また、富岳NEXTで開発されたハード・ソフト技術はモジュール化され、将来のシステムアップグレード時に部分的な交換や増設が容易になる可能性があります。特にGPUなどアクセラレータ部分は技術進歩が速いため、運用期間中により新しい世代のGPUへ置き換えることで性能向上を図ることも視野に入れられています(実際、NVIDIAはRubinの次の世代として“Feynman”アーキテクチャもロードマップに示唆しており、将来のアップグレードオプションとなり得ますnextplatform.com)。
国際競争力の面では、富岳NEXTが稼働する2030年前後には各国でポスト・エクサスケールの計算機が出揃うと予想されます。米国はエクサ級の先駆者としてさらに先を見据えた開発(例えばAI特化型の巨大クラスタ構想)を進めており、中国も独自路線でのエクサ超え計画が噂されています。その中で、日本の富岳NEXTが世界初の「ゼタ級HPC」として一番乗りできるかは未知数ですがxenospectrum.com、少なくとも**「シミュレーションとAIの統合性能」で世界最高水準を目指す**という明確な旗印を掲げた点でユニークな存在ですriken.jp。理研・富士通・NVIDIAの三者は、本機を世界市場にも展開し得る汎用プラットフォームに育てる構想を共有しておりriken.jp、開発された技術を他国のHPCやデータセンターにも供給することで国際標準をリードする意気込みですriken.jp。これは日本の技術を海外に売り込む好機であると同時に、海外の広いユーザコミュニティからフィードバックを得て富岳NEXTを継続的に洗練させるサイクルを生み出す狙いもあります。
最後に、富岳NEXTには日本の科学技術政策上の大義も託されています。それは「科学と産業の両面で不可欠な戦略技術を国内に持つ」という国家戦略ですriken.jp。HPCとAIは21世紀のデータ主権・技術主権を左右する重要分野であり、富岳NEXTを成功させることは日本がその分野で主導権を握ることにつながりますriken.jp。加えて、本プロジェクトを通じて国内半導体技術や人材育成にも波及効果が生まれ、将来的な産業競争力の底上げが期待できますriken.jp。富岳NEXTが予定通り稼働し所期の成果を上げれば、日本発の計算機が再び世界のトップクラスに返り咲くだけでなく、「シミュレーション×AI」による科学技術イノベーションのモデルケースを提示することでしょうdatacenterdynamics.com。それは、10年前「京」が達成し、富岳が引き継いできた理念――「社会と科学を計算で変革する」――をさらに発展させた未来像であり、日本が国際競争力を維持しつつ世界に貢献できる確かな足場になると期待されますasahi.com。
References: 富岳NEXT公式発表および関連報道よりriken.jpriken.jpdatacenterdynamics.comtomshardware.comblogs.nvidia.com等を参照。


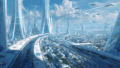
コメント